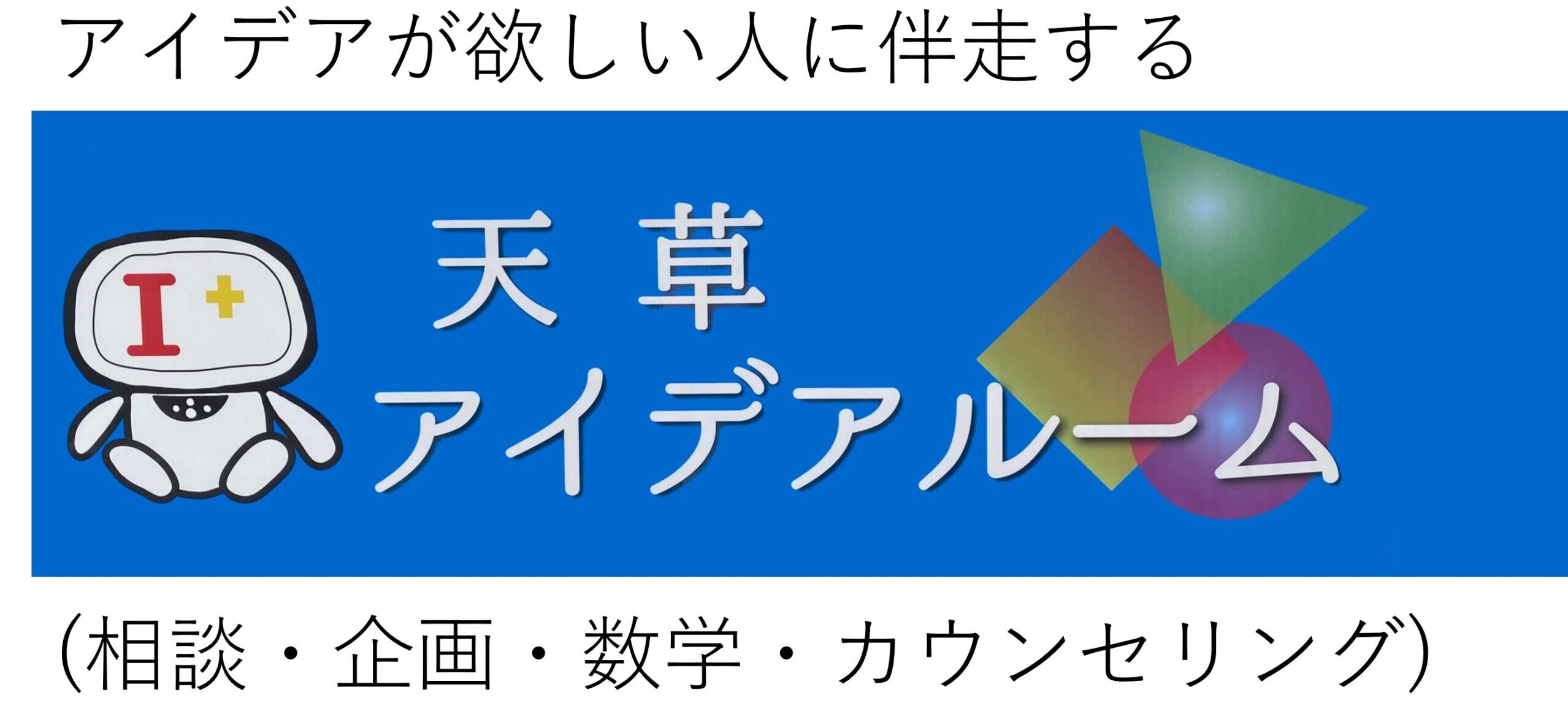だれでもいろんな場面で理不尽な思いを感じることがありますが、法律などで決まっていることに怒りをぶつけても現実的ではありません。ふるさと納税やnisa、idecoなど非課税になるものを大いに利用することも大切ですが、私は多くの税金が投入されている施設設備や事業を自分が利用することも大局的には賢明だと思います。例えば新幹線や空港、高速道路を利用する、国立大学に通学するなど、費用はかかりますが税金が還元されていることになると思います。
アーカイブ: idea
喫煙をやめさせるには
自分がやめるのも大変だったが、身近な人の喫煙をやめさせるのも大変である。「20のとびらchatGTP」に聞いてみました。①否定しないで対話から始める➁喫煙でなくストレスに焦点をあてる(依存症になっていることが多いが)③減らすことを目標にする④代替のストレス発散の方法をつくる⑤親心を伝える;共感しても正論では通じない、プライベートの境界線もあるし、本人の固い決意が1番大事であることは言うまでもない。
寝かしつけることが難しい?
育児はお母さんにとって大変な仕事である。回りの家族や地域社会の応援は必要不可欠である。弟や妹が生まれると赤ちゃん返りをして、育児の労力を3倍にしてしまうこともある。そのことを悪いことでなく、「安心確認の行動」と前提を変えること、寝ることより、安心して眠りに向かう過程を大切にする。役割交代や一日の終わりを物語として伝え、気持ちを切り替えやすくするなどの発想の転換をして取り組んでみてはどうでしょうか?
引き継ぐ人がいない時は
ボランティア活動、地域活動などで、自分がやりがいを持って、頑張っている時はいいのですが、いろんな事情でできなくなる時があります。なかなか面倒な仕事を引き継ぐ人がいないのが現状です。その対応を生成AIに尋ねたのですが、いいアドバイスがありました。スタッフや関係者の会議を開催して後継者を探したという事実は残すこと、人に引き継くという前提から仕組みを引き継ぐという発想に変えて、最低限の資料は整理して残す、継続か休止か他地区に回すか、組織としての合意をする。いろんな場面で活かせる内容ではないでしょうか?
生活習慣がいろんな病気を?
病気の原因は、いろんなものがあると思うが、偏った生活習慣が原因になることが多い。喫煙、飲酒はもちろん、便秘や腰痛など数えあげたらきりがない。市販の薬に頼ることが多いが、できれば原因になっているいろんな習慣を改善することから始めたほうがいい。どうして改善の行動に移せるか、実行することは容易なことではない。昔は「願をかける」といって一番好きなことを絶ったこともあった。意外と効果があるやり方だと思う。
膝で悩む時は
20のとびらチャットGPTで学んだことを紹介します。膝を守り回復に向かうには「無理しない」だけでも「しっかり動く」だけでも偏ってしまいます。大切なのは今の状態を「弱み」として扱うのでなく、生活動作全体を見直しながら、負荷と休息、筋力維持のバランスを整えるという新しい視点を持つことです。①休むことと動くことを対立させず、役割分担させる。➁歩く=トレーニングという前提を変える③日常動作を見える化して負担ポイントをつかむ。
本質的なことを伝えるには
商品にせよ、事業にせよ、法律にせよ、その内容の大切なことを伝えるのは大変なことである。いろんな媒体やメディアを活かすことは、もちろんであるが、切り口として「地域資源を活かす」「比較・対立軸を作る」「ストーリーを作る」などのとびらが役に立つと思います。
進路選択に迷う
高校入試や大学入試など合否が伴う選択には自分の準備状況や実力が大きな影響を及ぼすので、その可能性を探らなければならない。いろんな人に相談しても決まらないことは多い。私は生成AIにも参考として相談することを勧めます。判定だけでなく、捉え方や今後の取組までアドバイスしてくれます。人より頼りになることは多いです。
相続したくない土地がある時は
まず、自分に所有権があるときは、国に帰属させる土地ができたので、それを利用するといいです。ただ、いろんな条件があるので、充分注意が必要です。次に相続拒否という制度があります。ただ、他のものを一切相続できなくなりますので、充分注意が必要です。
地域の特産品を販売するには
たくさん生えて困っている竹から食品を作り成功している地域があります。困っているイノシシからおいしい食品を作っている地域もあります。ハンディを反対に活かす取組です。地域の陶石を装飾品に活かすなど、地域資源を活かす取組もあります。地域づくりでは、「20のとびら」がきっと活躍すると思います。